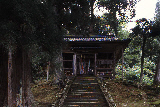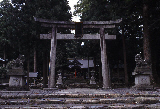| 越前市の感じどころ 神社・仏閣ーー> 地図はこちらから(越前府中の歴史) 資料提供 越前市観光振興課 |
正覚寺 京町二丁目1-8 0778-22-1319
 |
南北朝期に越前守護斯波高経がここに新善光寺城を築き、1338年新田義貞に攻められ消失しました。その城跡に1366年、良如は、乱で戦死した数千人の霊を弔うため浄土宗の寺院を建立しました。 |
|
【周辺施設】
千代鶴神社(京町二丁目)
引接寺(京町二丁目)
国分寺(京町一丁目)
総社大神宮(京町一丁目)
寺町通り(京町)
|
龍泉寺 深草一丁目10-3 0778-22-4586
 |
1368年、通幻寂霊(つうげんじゃくれい)が開いた曹洞宗寺院。江戸時代には府中領主・本多家の菩提寺となり、本多家歴代の墓があります。また、徳川家康・秀忠・結城秀康像などの指定文化財を有しています。 |
|
【関連スポット】本多家
藤垣神社(本多三丁目)
金剛院(深草二丁目)
本保陣屋跡(本保町) |
千代鶴神社 京町二丁目4
 |
およそ700年前に京都の刀匠千代鶴国安が当地に移り住み、刀を打つかたわら鎌の改良に努めて越前打刃物の基礎を築きました。また、千代鶴の池は国安が刀を打つ水を汲んだと伝えられている井戸です。 |
|
【関連スポット】越前打刃物
越前打刃物会館(池ノ上町)
タケフナイフビレッジ(余川町) |
引接寺 京町三丁目3-5 0778-22-0442
 |
戦国時代の1448年、天台真盛宗の開祖真盛(しんせい)により草創された、天台真盛宗別格本山。山門の豪華さは市内に例を見ず、鯉の滝登りの小脇彫や欄干の羅漢などの彫刻が見事。境内には戦国時代の石仏や江戸時代末の石大仏があります。このほか境内には、明治32年に建築された福井警察部庁舎を移築改修された丈生幼稚園があります。 |
|
【関連スポット】武生の三大仏
月光寺の銅製大仏(南一丁目)
霊泉寺の木大仏(池泉町)
|
|
国分寺 京町一丁目6-2 0778-22-3088
 |
奈良時代の天平13年(741)聖武天皇の勅願により諸国の国府に国分寺が建立されました。創建当時の場所は確定されていないが、広大な敷地に立派な建物が甍をつらねていたものと思われます。大虫廃寺跡を国分寺跡とする説もあります。 |
|
【関連イベント】
節分会・豆まき式(2月3日)
お砂踏み(5月8日〜15日)
【周辺施設】
千代鶴神社(京町二丁目)
引接寺・正覚寺(京町二丁目)
総社大神宮(京町一丁目)
寺町通り(京町)
|
御霊神社 本多一丁目3-1
 |
祭神は桓武天皇の皇子、崇道天皇(早良親王)。政争に巻きこまれ、いわれなく死に追いやられた早良親王のたたりをおそれ霊を鎮めるために、全国の国司に御霊神社の建立の詔勅が出されたという。総社、国分寺と同じように御霊神社があるのは、その地に国府があった証拠だといわれています。 |
|
【周辺施設】
藤垣神社(本多三丁目)
金剛院(深草二丁目)
龍泉寺(深草一丁目)
|
|
金剛院 深草二丁目2-37 0778-22-7188
 |
永享5年(1433)に開かれ安泰寺と称したが、天正年間に焼失し、後に領主青木紀伊守におり再建された。慶長15年(1610)の府中領主本多富正により青木氏の城跡の現在地に移された。また、毎年7月15日に行われる「みたま祭り」では、6,000本のろうそくの灯りの中、僧侶が経を読みながら歩き、幽玄な雰囲気が漂う。 |
|
【関連イベント】
みたま祭り(7月15日)
【関連スポット】本多家
龍泉寺(深草一丁目)
藤垣神社(本多三丁目)
本保陣屋跡(本保町)
|
|
藤垣神社 本多三丁目3-3 0778-22-3106
 |
江戸時代の府中(武生)領主本多家の初代本多富正を祀った神社。富正は、戦国時代に荒れ果てた府中の街並みを整備し、産業を保護奨励し、現在の市街地の基礎を築いた人物で、神社には富正ゆかりの刀・手紙などが残されています。 |
|
【関連スポット】本多家
龍泉寺(深草一丁目)
金剛院(深草二丁目)
本保陣屋跡(本保町)
|
|
総社大神宮 京町一丁目4-35 0778-22-1127
 |
市街地のほぼ中央に位置する総社大神宮。古代に国司は、各社の神々を勧請して総社を建立し、総社に詣でることによって、各社の巡拝に替えたといわれています。春の「おはいごさん」、夏の「茅の輪くぐり」、秋の「総社まつり」などの祭礼には多くの参拝客が訪れます。拝殿は入母屋造りのいずれも銅板葺きで、国府の社の風格が感じられます。 |
|
【関連イベント】
おはいごさん
茅の輪くぐり(7月1日)
総社大神宮祭礼(9月15日)
【周辺施設】
国分寺・引接寺・寺町通り(京町)
|
|
円宮寺 あおば町2-41 0778-24-2758
 |
文明4年(1472)、蓮如上人の教化により天台宗から浄土真宗に改宗した。天正3年(1575)、織田信長による越前一向一揆攻めのときには、円宮寺の住職了観は武生の一揆軍の大将として戦った。毎年、蓮如上人の絵像を輿車に納めて、京都の東本願寺と福井県あわら市の吉崎御坊の間を徒歩で往復する行事の際には、円宮寺で一泊します。 |
|
【周辺施設】
神明神社(若竹町)
月光寺(南一丁目)
窓安寺(南三丁目)
|
久成寺 平和町2-5 0778-24-3991
 |
天文15年(1546)、呉服商として名を馳せた小袖屋山本次郎右衛門久成が、一族の菩提寺として建てた寺。境内は庭園風のしつらえで、寺らしくない雰囲気。本堂入り口の柱の上部に辺りをにらむ眼光鋭いみごとな龍が彫られています。 |
|
【周辺施設】
龍門寺・大宝寺(本町)
河濯山芳春寺(高瀬二丁目)
宝円寺(高瀬一丁目)
|
河濯山芳春寺 高瀬二丁目5-15 0778-22-1586
 |
大日如来を本尊にまつる、越前市で唯一の臨済宗大徳寺派の寺です。古くはすぐそばのを川で身を清めてからお参りをしたことから、河濯と呼ばれるようになりました。通称「かわっさん」と呼ばれ、安産・病気快癒にご利益があるといわれています。また7月30日、31日には河濯山まつりが行われ、多くの参拝客でにぎわいます。 |
|
【関連イベント】
河濯山芳春寺祭礼、河濯権現祭
(7月30日、31日)
【周辺施設】
龍門寺・大宝寺(本町)
宝円寺(高瀬一丁目)
久成寺(平和町)
|
帆山寺 住吉町1-24 0778-22-4074
 |
ご本尊は千手観音。奈良時代に高僧泰澄大師の作と伝えられます。33年ごとのご開帳で、平成10年がその年にあたった。帆山寺は、いろいろな仏様が祭られているので、ゆっくりと拝観したい。たとえば、本堂に入ったすぐ左手に安置されている涅槃仏や、「おびんずるさん」と呼ばれる撫で仏は自分の体の悪い部分と同じところをなでると治るという。 |
|
【周辺施設】
武生公会堂記念館(蓬莱町)
ちひろの生まれた家記念館(天王町)
|
宝円寺 高瀬一丁目27-4 0778-22-1645
 |
嘉慶2年(1388)正祖禅師が創建した曹洞宗の寺院で、天正年間に府中三人衆の一人であった前田利家がこの寺を保護した。前田利家は、その後、能登に次いで加賀百万石を領したが、金沢にも宝円寺を創建した。墓地に前田利家の両親の供養塔があります。 |
|
【関連スポット】利家と府中三人衆
龍門寺(本町)
小丸城跡(五分市町)
|
月光寺 南一丁目2-12 0778-22-6367
 |
天保年間(1830〜44)の大飢饉の際の武生近辺の餓死者の供養のため、弘化4年(1847)に有志により建立された銅製の大仏が安置されています。当初は露仏でしたが、天台真盛宗引接寺住職今川良順が、堂宇を建立しました。 |
|
【関連スポット】武生三大仏
引接寺の石大仏(京町)
霊泉寺の木大仏(池泉町)
|
神明神社(上総社) 若竹町11-19 0778-22-4654
 |
第26代継体天皇の時代、この地に社跡があったので、天照皇大神を祭る社が建立された。しかしその後の戦乱の世で荒れ果てたため、寛文年間(1661〜)に領主本多昌長によって再建された。この場所で日野山を拝み、旅人たちが旅の無事を祈願したことから、「ふしょうがみさん」の愛称で地元の人たちから親しまれています。 |
|
【周辺施設】
円宮寺(あおば町)
月光寺(南一丁目)
窓安寺(南三丁目)
|
窓安寺 南三丁目1-5 0778-23-0439
 |
天台宗の寺院で、朝倉氏の帰依を受けたと伝えられ、(朝倉時代)室町後期に現在の地に移ったと伝えられています。朝倉時代の石仏2体が残っています。 |
|
【周辺施設】
円宮寺(あおば町)
月光寺(南一丁目)
神明神社(若竹町)
|
龍門寺 本町9-5 0778-22-2215
 |
龍門寺の創建は、正安元年(1299)と伝えられています。その後築城され、織田信長は、天正元年(1573)の朝倉攻め、同3年(1575)の一向一揆殲滅の本陣として使い、天正3年より府中三人衆の一人不破光治の居城となった。同16年(1588)城跡に曹洞宗龍門寺が再建されました。現在でも堀や土塁の跡を見ることができます。 |
|
【関連スポット】利家と府中三人衆
宝円寺(高瀬一丁目)
小丸城跡(五分市町)
|
毫攝寺 清水頭町2-9 0778-27-1224
 |
かつて与謝野鉄幹・晶子夫妻が訪れ、いくつかの歌を残しているこの寺は、真宗出雲路派の本山。山門、御影堂、阿弥陀堂、経蔵、鐘楼、客殿からなる大寺院で、そのたたずまいは圧巻。8月27日、28日の当山の大寄りは、多くの参拝客でにぎわいます。 |
|
【関連イベント】
大寄り(8月27日、28日)
【周辺施設】
越前の里味真野苑(余川町)
万葉菊花園(余川町)
タケフナイフビレッジ(余川町)
|
小丸城跡 五分市町
 |
1580年頃に織田信長の家臣、佐々成政(さっさ なりまさ)によって築かれた城跡。内堀・外堀も造られ城全域は東西300メートル、南北350メートルといわれています。現在は本丸跡と土塁・堀の一部が残っています。 |
|
【関連スポット】利家と府中三人衆
宝円寺(高瀬一丁目)
龍門寺(本町)
【周辺施設】
城福寺(五分市町)
毫攝寺(清水頭町)
越前の里味真野苑(余川町)
万葉菊花園(余川町)
タケフナイフビレッジ(余川町)
|
城福寺 五分市町11-26 0778-27-1773
 |
国の名勝に指定された「城福寺庭園」は、江戸時代中期、元禄年間に造られた「借景築山式蓬莱枯山水(しゃくけいつきやましきほうらいかれさんすい)」の苔庭です。春は椿、初夏には苔の緑に躑躅(つづじ)が映え、秋は紅葉、初冬は柊(ひいらぎ)の大木(市指定天然記念物)に一斉に咲く花は一足早い雪を思わせます。 |
|
【施設情報】
拝観料 大人300円、学生200円
【周辺施設】
小丸城跡(五分市町)
毫攝寺(清水頭町)
越前の里味真野苑(余川町)
万葉菊花園(余川町)
タケフナイフビレッジ(余川町)
|
霊泉寺 池泉町11-26 0778-27-1118
 |
鞍谷御所跡に近い霊泉寺は、応仁の乱(1467〜77)の時、弟義廉と斯波氏の相続を争って越前に下ったといわれる斯波義敏が文明10年(1484)に出家して興してと伝えられています。また、ここには木造の大仏が安置されています。 |
|
【関連スポット】武生三大仏
引接寺の石大仏(京町)
月光寺の銅製大仏(南一丁目)
【周辺施設】
霊泉寺(池泉町)
越前の里味真野苑(余川町)
万葉菊花園(余川町)
タケフナイフビレッジ(余川町)
|
味真野神社 池泉町21-18
 |
継体天皇を祭る神社。継体天皇は即位する前に味真野で暮らしていたという伝承があります。世阿弥の作った謡曲「花筐」は、味真野を舞台に美しい女性照日の前の継体天皇への激しい恋を描いています。室町時代には鞍谷氏の城館があり、境内の北と西に土塁の一部が残っています。 |
|
【関連イベント】
越前万歳初舞(1月1日)
【関連スポット】継体大王
五皇神社(文室町)
子安観音(文室町)
越前の里味真野苑(余川町)
花筐公園・薄墨桜(粟田部町)
岡太神社(粟田部町)
皇子ヶ池(粟田部町)
|
五皇神社 文室町 0778-27-1341
 |
応神天皇から継体天皇の父彦主人王までの5柱の御神霊を祀る神社。男大迹王(継体天皇)が学問所として開いたという伝説も残されています。毎年4月18日には奇祭「ほうき祭」が行われ、ほうきで石段や境内を掃き清めて参拝すると、腹痛が治るとも言い伝えられています。 |
|
【関連スポット】継体大王
味真野神社(池泉町)
子安観音(文室町)
越前の里味真野苑(余川町)
花筐公園・薄墨桜(粟田部町)
岡太神社(粟田部町)
皇子ヶ池(粟田部町)
|
子安観音 文室町 0778-27-2423
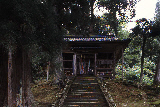 |
正高寺の奥院に安置されているのが子安観音です。本来は如意輪観世音菩薩と言われ、天竺(インド)の建築を司る天神の作で、三国伝来の仏様とも伝えられています。考養心の厚い継体天皇の子、欽明天皇がこの地に安置し、現在では安産や子授けの霊験あらたかな観音として、各地から参拝客が訪れています。 |
|
【関連スポット】継体大王
味真野神社(池泉町)
五皇神社(文室町)
越前の里味真野苑(余川町)
花筐公園・薄墨桜(粟田部町)
岡太神社(粟田部町)
皇子ヶ池(粟田部町)
|
岡太・大滝神社 大滝町 0778-42-1151
 |
権現山の頂上にある奥の院とその麓に建つ国の重要文化財の下宮があります。奥の院には紙祖神岡太神社と大滝神社の両本殿が並び建ち、里宮はこれを併せて祀っています。紙祖神岡太神社は、1500年ほど前この里に紙漉きの技を伝えた川上御前を全国で唯一の紙祖神として祀っています。 |
|
【関連イベント】
神と紙のまつり(5月3日〜5日)
大滝神社祭礼(10月11日〜13日)
【周辺施設】
昔の町並み(五箇地区)
和紙の里通り(新在家町)
パピルス館
卯立の工芸館
紙の文化博物館
|
岡太神社 粟田部町19-2 0778-43-1626
 |
粟田部にある神社。継体天皇ゆかりの神社として知られています。毎年2月11日行われている蓬莱祀は、継体大王が樟葉宮で即位されたことを祝って行われるお祭りです。 |
|
【関連イベント】
左義長祭(1月上旬)
市祭り(2月9日)
蓬莱祀(2月11日)
堂の餅(10月12日)
【関連スポット】継体大王
味真野神社(池泉町)
五皇神社・子安観音(文室町)
越前の里味真野苑(余川町)
花筐公園・薄墨桜(粟田部町)
皇子ヶ池(粟田部町)
|
高善寺 北坂下町5-23 0778-42-1478
 |
佐々木小次郎の生家といわれる高善寺は、永觀元(983)年に覚勝阿闍梨を開基とする古刹で、今は浄土真宗の寺。歴代住職は、源頼朝に大きく貢献した宇多源氏一族・佐々木四郎高綱の末裔と伝えられ、代々佐々木姓を名乗っています。また、高善寺の家紋は、佐々木小次郎と同じ角立四ッ目菱(すみたてよつめびし)です。 |
|
【関連イベント】
小次郎まつり
【関連スポット】佐々木小次郎
小次郎公園(北坂下町)
柳の滝(柳元町)
|
朽飯八幡神社 朽飯町22-33
 |
この神社は服部郷朽飯(くだし)にあり、機織の神社として注目されています。顕宗天皇(485〜487)の時に百済国努理使主の孫で阿久太の男の弥和をはじめ、機織の技術に長じた織姫たちが養蚕と機織の新しい技術を郷民に教え、生業として栄えたところから祭神として天万栲幡千比売命(たくさんの機織の神様)を祀ったといわれています。朽飯の地名は、命、管師、また、クダシは久太が志の略で継体天皇の妃倭媛(ヤマトヒメ)の子、久高の王の名であるとする説があります。 |
|
【注目イベント】
式年大祭(33年毎)
平成23年に第40回式年大祭開催
|
日野神社 中平吹町80-1-1 0778-21-2335
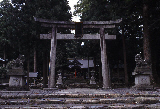 |
越前富士とも呼ばれ、古くから信仰の山であった日野山の登山口にある神社。山頂に奥宮があります。夏に行われる「日野山まつり」には拝殿で御神楽を奉納したあと、夜を徹して登山。かがり火をたいて夜をあかし、ご来光を拝まます。絵馬殿では、寛文5年(1665)に奉納された日本最古の「四季耕作図」の絵馬を見ることができます。 |
|
【関連イベント】
日野山まつり(7月第三土曜日)
|
本保陣屋跡 本保町
 |
江戸時代の越前市域には本多家が治める府中領をはじめ、幕府の直轄地や他藩の領地が複雑に入り交じっていた。同じように越前には直轄地や私領が混在していた。そういった歴史を今に伝えているのが本保陣屋跡です。 |
|
【関連スポット】本多家
龍泉寺(深草一丁目)
金剛院(深草二丁目)
藤垣神社(本保町)
|
大塩八幡宮 国兼町 0778-23-8074
 |
この社は891年に宇多天皇の勅命により建立されたと伝えられ、1183年には木曽義仲(きそよしなか)が平家追討のため、本陣を置いたとも。境内には苔が密生し、四季を通して参拝者の目を楽しませてくれます。拝殿は室町期の建物で、国の重要文化財に指定されています。 |
|
【周辺施設】
しきぶ温泉「湯楽里」(白崎町)
白崎公園(白崎町)
|
大虫神社 大虫町 0778-22-5041
 |
崇神天皇(すじんてんのう)7年の創建と伝えられ、平安時代の「延喜式(えんぎしき)」に式内大社として記されている古社。木造男神坐像(もくぞうだんしんざぞう)・伝天津日高火子穂々出見命(でんあまつひこひこほほでみのみこと)と伝塩推神(でんしおづちのかみ)は、平安時代の作で国の重要文化財です |
|
【周辺施設】
鬼ヶ岳登山口(大虫町)
大虫の滝(大虫町)
|
卍の辻 本町
 |
龍門寺近くにある「卍の辻」。中央が小さな広場になっており、どの道からも見通しがきかないようになった特殊な四つ辻で、戦国時代、攻めにくいように戦術的に作られたのではないかといわれています。 |
|
【周辺施設】
龍門寺・大宝寺(本町)
久成寺(平和町)
河濯山芳春寺(高瀬二丁目)
宝円寺(高瀬一丁目)
|
札の辻 蓬莱町
 |
現在もいろいろな催しの案内が掲示されている「札の辻」は江戸時代、幕府の禁止事項などを告知した高札を掲げた小屋があった場所です。 |
|
【周辺施設】
蔵の辻(蓬莱町)
武生公会堂記念館(蓬莱町)
寺町通り(京町)
ちひろの生まれた家記念館(天王町)
|